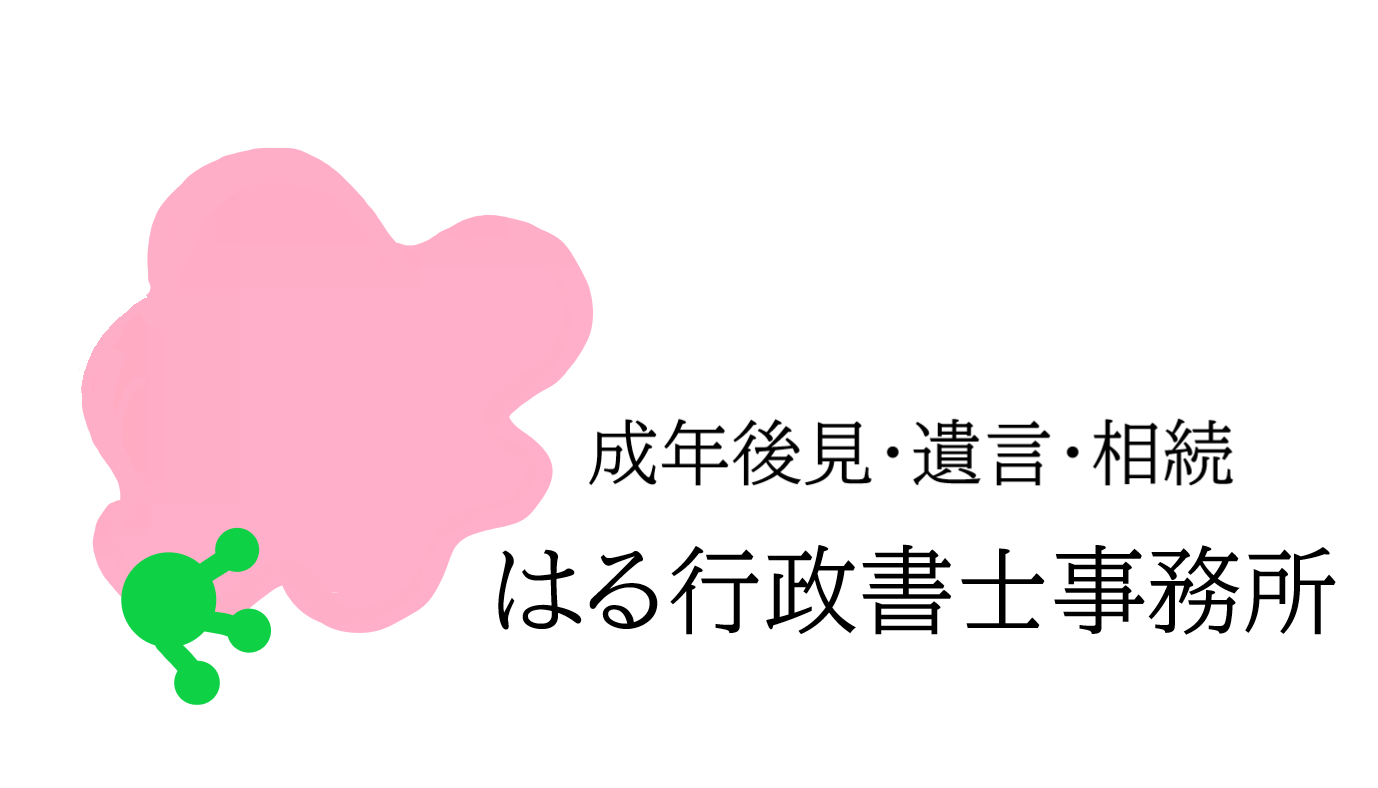成年後見人という仕事のやりがい
本人との信頼関係を築く
成年後見人は、大切な財産を預かり、暮らしや身体に関する契約のお手伝いをすることで、ご本人の生活を整える役割を持っています。
判断能力がなくなった後に財産を預けたり自分の生活のことを決めてもらったりするわけですから、信頼する人にしてもらいたいのが当たり前だと思います。
任意後見の場合は、ご本人と何度も面談しコミュニケーションをとり、信頼関係を築いたうえでの「契約」ですから、お互いのことはある程度理解しており、後見をする側もされる側も安心感がありますが、専門職後見人として法定後見を受任する際は、まったく知らない方を後見していくことになります。
ですので、初めて被後見人になるご本人にお会いするときは、信頼関係が築けるか心配ですし、こちらもとても緊張します。
後見人に選任された際にある程度の情報は得ており、それをもとにご本人とできるだけコミュニケーションをとりながら後見をしていくことになるのですが、ご本人が認知症であり、また人間ですからいろいろな特性を持っていますので、信頼関係を築くのがなかなか難しい方もいらっしゃいます。
Aさんのおはなし
私が以前後見人に就いたAさんの事例です。
Aさん(84歳男性)
未婚・子供なし
持ち家に一人暮らし
親族とは疎遠
ご近所や地域とは関わりがない
Aさんは長いこと一人暮らしをしていましたが、歳を重ねるごとに頑固になっていき、ご近所とトラブルを起こしたり、気に入らないことがあると手をあげたり暴言を吐くようになってきました。
地区の中でも困りものとして扱われるようになり、また、自宅がゴミ屋敷化してきて火災などの心配もある、さらに動物も数匹飼っているが世話をしきれていない、認知症の症状もでているようだということで、行政が地区と連携して対応に当たっていましたが、本人がすべての関わりを強く拒否するので、なかなか支援に入れなくて各方面が不安を抱えている事案でした。
そんな綱渡りで暮らしていたある日、Aさんが体調不良を訴え救急車で運ばれ、そのまま入院することに。
入院中も「家に帰る!」「俺を閉じ込めやがって」など病院スタッフや行政職員に暴言を吐き、ケアスタッフに手を挙げる日々…
身体的な介護度も3がつき、さらに「不穏」と呼ばれる状態と判断され、精神薬の投与が始まりました。
薬の効果もあってすこし落ち着いたころ、行政職員と民生委員さんが本人と話しあい、みなで自宅を見に行き、現状をAさんに認識させ、一人暮らしを続けるのは難しい、施設に入らなくては生活できない、となんとか納得させるにいたりました。
しかし施設に入るためには身元保証人が必要です。
(本来は必要ありませんが、ほぼ全ての施設で求められ、いない場合は入居できません)
成年後見人は身元保証人ではありませんが、行政としてはそれも含めて本人の世話をしてくれる人、という感覚で後見の申立てをし、縁があって私がAさんの後見人に就職することになりました。
Aさんとの初めての面談
暴言、暴力、不穏、ゴミ屋敷…
そういったパワーワードを前に、ご本人と初めて面談するときはとても緊張しました。
後見人であることをわかってもらえるかな、理解してもらえるかな、暴言、暴力があったら怖いな、何をお話ししよう…
車いすに乗せられてやってきたAさんは見た目にも相当弱っているような感じでした。
目がとろんとして車いすにまっすぐ座っていられないし、こちらの問いかけにはほとんど反応せず、お話しできないなら筆談で、と紙を渡しても手が震えて書けない。
初回の面談は暴言、暴力などは皆無でしたが、何か異常なものを感じました。
普通に老化や認知症によって体力気力が落ちている高齢者ではないと思いました。
Aさんが精神薬を4種類も投与されているということを知ったのは面談が終わった後でした。
言葉を発しなかったのも、精神薬によって無気力な状態が続き、体力が非常に落ちているからでした。
不穏が続けば病院でもお世話できないし、本人も消耗が激しいので仕方がないことなのかもしれません。
また、減薬したり薬を変更するのもお医者さんの判断です。
Aさんの後見人になりたての私にはショックでした。
それからも月に1度は面会に言ってAさんの顔は見ていましたが、こちらの問いかけにはほとんど反応がなく、口を開けて車いすに座っているだけ。
Aさんの大好きな甘いもの、ようかんやゼリーやプリンなどを差し入れし、主にお世話をしてくれている施設スタッフとお話しして帰ってくる、という日々が続いていました。
Aさんとの関係の変化
Aさんは施設で何度か発熱をしており、そのたびに主治医の判断で精神薬が減らされ、私が後見を初めて数か月後には全く処方されなくなりました。
その後、夏のある日の面会も、これまでと同じようにぼんやりしているAさんにこちらから一方的にお話しして、「また来月来るからね」と本人の目の前で手を振ったところ、なんとAさんも手を振ってくれたのです。
あまり上がらない手をあげて、ぎこちなくゆっくり左右に振られた右手。
うれしくてAさんの肩をたたいてしまいました。
自宅で一人で暮らしていたときは、周囲に毒づいてばかりいて避けられていたAさん。
そんなAさんが誰かに手を振ることがあるなんて、想像もしていませんでした。
後見人の存在を認めてくれたんだな、と思い、とてもとてもうれしくて涙が出そうでした。
精神薬をやめたことも影響していたのかもしれません。
翌月の面会でも手を振ってくれるかな、楽しみだな、何を差し入れしてあげたら喜ぶかな、そんな風に気持ちがうきうきしました。
しかし「また来月」は来ませんでした。
Aさんはその後誤嚥性肺炎を発症し、急に亡くなってしまったのです。
Aさんの死から教えられたこと
Aさんには死後の葬儀や事務をしてくれる親族がいなかったため、私が後見人として火葬や納骨も行いました。
お骨を拾ったのも私一人でした。
84年生きてきて、最後を見送るのが後見人ただ一人なんて…
人はやはりひとりでは生きることも死ぬこともできない。
普段から誰かと関わって、おたがいさまでお世話しお世話されながら生きていくことが必要です。
意地を張って、自分から孤独を選んで、Aさんは幸せだったのかなあ…
私に手を振ってくれたAさんが本来のAさんで、暴言や暴力で自ら周りを遠ざけていたころは本当はさみしかったんじゃないだろうか。周囲とうまく関係を築けなくて困っていただけなんじゃないか。
もっと人と関わりながら生きていける方法があったんじゃないか。
早めに、適切な支援があればもっと幸せな老後が迎えられたんじゃないか。
Aさんは自宅にいたとき猫3匹と犬1匹を飼っていて、入所を決めた際に行政の手で保健所に引き取ってもらったとのこと。
入所後お部屋でテレビを見ていて犬が出てくるたびに涙を流していたそうです。
そんなことも思い出し、今でも切なくなります。
何が幸せかはもちろん人によって違いますし、Aさんの気持ちはわかりませんが…
少なくとも、心から悼んでくれる人がひとりもいないという人生はさみしすぎます。
せめて、Aさんが、「後見人がおれの後始末してくれていがったやー」と思ってくれているといいな。
成年後見をしていると、他人の人生に死後まで関わることになりますので、教わることがたくさんあります。
Aさんから教わった大きなことは「死にかたは生きかたの鏡」ということです。
Aさんから経験させていただいたことも糧にして、どんな過去があろうと、今がたいへんな方でも、最後に「後見人がついてくれて良かった」と思ってもらえるような後見をこれからもしていきたいと思っています。