高齢者等終身サポート事業者ってなに?
増えている身元保証問題
病院への入院や、施設等への入所で必ずと言っていいほど求められる身元保証人。
ですが、そもそも身元保証を強制する法律はありません。
本来必要ないものですが、病院や施設は、費用の支払いや身元の引き受け、残置物の引取りを担保するために身元保証人を要求するようです。
本人に何かあった際、代わりに本人の事務をやってくれる人の意味合いですね。
近年の家族関係の変化から、この身元保証人を立てられない方が増えています。
家族がいるけれど遠くに住んでいて緊急対応できない、疎遠でお願いできない。そもそも家族がいない、など。
そういった不安に対応してくれるとしていつごろからか増えてきたのが身元保証をうたう事業者です。
高齢になるとただでさえ心身ともに不安や心配事が増えるもの。
身元保証だけでなく、そういった老後の心配事にも対応しますよ、また死後の後始末などもしますよ、という業者があまた存在するようになりました。
そのような業者を総称して
高齢者等終身サポート事業者
と言います。
どういったことをサポートしてくれるのかと言うと、
- 通院の送迎・付き添い
- 入院・入所の際の連帯保証
- 入退院・入退所の際の手続きの代行
- 亡くなった際の身柄の引取り
- 緊急連絡先への指定
- 葬儀に関する事務
- 生前の費用の清算
- 自宅等不動産の始末
- 行政手続きの代行 など。
通常家族が行う様々な事務を代行してくれます。
しかし、そういった業者のなかには高齢者のお金目当てで、実際にはろくにサポートをしなかったり、死後に遺産を寄付させることが契約の条件となっていたり、預かり金を着服したあげくに倒産してしまったりと、消費者被害を引き起こす会社も存在し、社会的な問題となっていました。
そこで、厚生労働省を中心に、令和6年6月に
という、事業者を選ぶ際の目安となるものが策定されました。
高齢者等終身サポート事業者ガイドラインとは
○ 高齢者等終身サポート事業者の適正な事業運営を確保し、高齢者等終身サポート事業の健全な発展を推進し、利用者が安心して当該事業を利用できることに資するようにするため、本ガイドラインを策定することとしたものである。
○本ガイドラインは、高齢者等終身サポート事業者の参考となることはもとより、利用者による事業者判断の目安ともなり得るものである。
高齢者等終身サポート事業者ガイドライン「第1全般的な事項 1ガイドラインの目的 より」
契約を結ぶにあたって留意すべき点が細かく記載されていますので、健全な事業者かどうかの見極めにある程度の指標ができたことで、消費者の側としては選びやすくなったとは言えます。
また、このガイドラインを遵守している業者であれば、それを明示していますので、一応の安心は担保されているとは言えます。
ガイドラインがあっても…
「自分ひとりで」問題のない業者を選ぶことはできるか
しかしこのような事業者を必要とする時は、すでに不安を抱いている状況で、自分の不安を解消してくれるといううたい文句を見たときに、冷静にこのガイドラインを確認したうえで判断しよう!と思えるでしょうか。
事業者の話を聞いて100%内容を理解して契約にいたることができるでしょうか。
他の似たような事業者を比較検討して、より自分の条件に合った事業者を選ぶという作業ができるでしょうか。
自分にこの高齢者等サポート事業者が必要かもしれない、と思った時は、ある程度の高齢になっており、ベストな選択を自分ひとりですることが難しくなっている方が多いと思われます。
このガイドラインは法的拘束力のあるものではなく、守ってね、程度のことですので、ガイドラインに乗っ取っていない業者が甘い言葉で近づいてくることは考えられることです。
必要なのは、自分の判断が間違っていないか相談できる相手なのではないでしょうか。
身元保証だけで安心な老後を送ることはできるか…
現代の社会は核家族化や晩婚化、未婚率の増加、超高齢化に少子化と、盛りだくさんの社会課題の中、家族のつながりが確実に薄くなってきています。
隣近所との関わりや友人関係の希薄さという、地域や社会でのつながりも同様です。
お世話してくれる人がいないのに何も備えておかなければ、ご自分の尊厳を守りながら生活するのは非常に難しくなります。
そのため、お金を払えば第三者に身元の保証等老後の事務や死後のことを託せるというサービスがあって、そのサービスを委託した会社が適切に動いてくれれば、何かあっても途方に暮れる状況になることはないでしょう。
しかし、物理的な安心は備えられるかもしれませんが、精神的な安心はどこに求めればいいのでしょうか。
まれに、ピンピンコロリでまったく誰のお世話にもならず亡くなる方はいますが、どのように老いて亡くなるかは自分で知ることはできません。
何かあった時にだれも頼る人がいない、というのはどれだけ不安なことか。
その気持ちに寄り添ってくれるのが高齢者等終身サポート事業者であれば問題ありません。
しかし、相手は法人ですから、身近にいていつでも相談に乗ってくれる相手ではないかもしれません。
頼れる身内がいない方は、やはり地域のつながりを持つことが大切です。
お住まいの地区の包括支援センターや地区の民生委員さんなどに自分のことを伝えておけば、見守りをしてくれますし、困った時には制度の紹介や適切な担当へとつないでくれるでしょう。
お金で事務的なことの安心は買えるかもしれませんが、孤独や孤立を防ぐことはできません。
それらを防げれば、フレイル状態や認知症になることも防ぐ効果があります。
結果健康寿命も延び、ピンピンコロリに近づけるかもしれません。
身元保証への心配についても、当事務所にご相談ください
はる行政書士事務所では、ご相談を傾聴して、適切な制度につなぐことをいちばん大切にしています。
依頼者様の心配ごとや不安を丁寧にお聴きして、どんなサポートや制度であればいちばんご希望をかなえられるかをご提案させていただいております。
頼れる身内がおらず身元保証が心配だ、と来られた方でも、よくお聴きしてみると必要なのは身元保証ではなかったりします。
また、身元保証会社に高額を支払って頼まなくても、
「移行型任意後見契約」
を結ぶことで、だいたいの課題がクリアできることが多いです。
移行型任意後見契約で行政書士が行うサポートは、高齢者等終身サポート事業者と似たような内容の業務になりますが、私たち行政書士は国家資格者として、行政書士法等各法律に基づいた規制と高い倫理観を持ち合わせているため、会社として利益を出すために事業をしている法人が行うサポートとは、異なるものです。
どちらが依頼者様に必要か、どのような違いがあるかも含めてお話させていただいておりますので、不安がある方はぜひご相談ください。
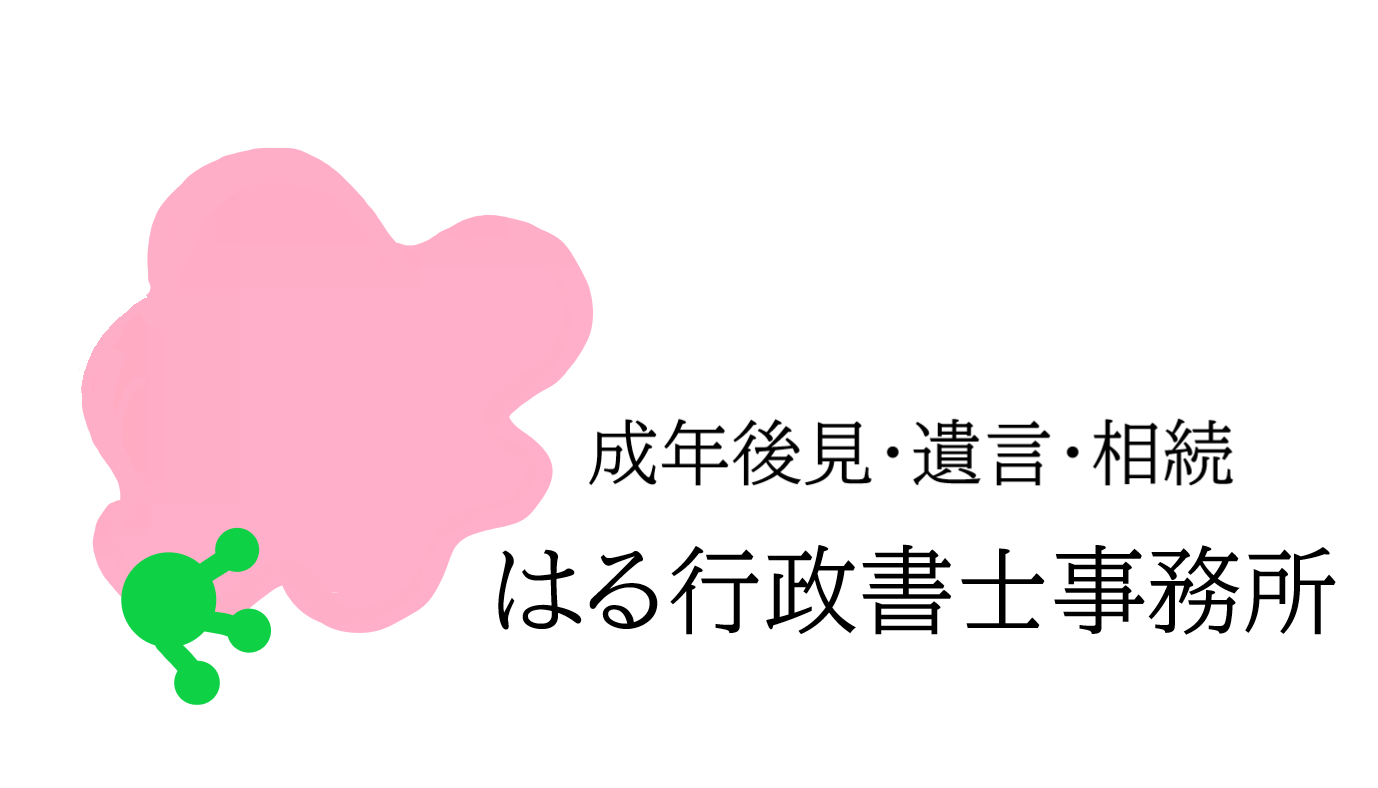


“高齢者等終身サポート事業者ってなに?” に対して1件のコメントがあります。